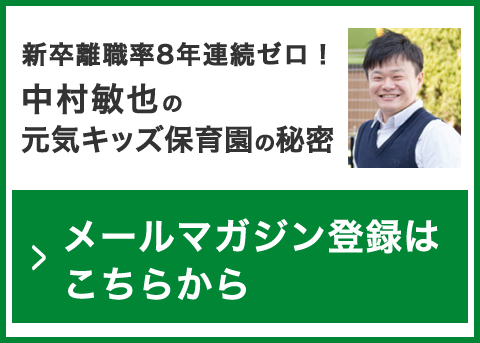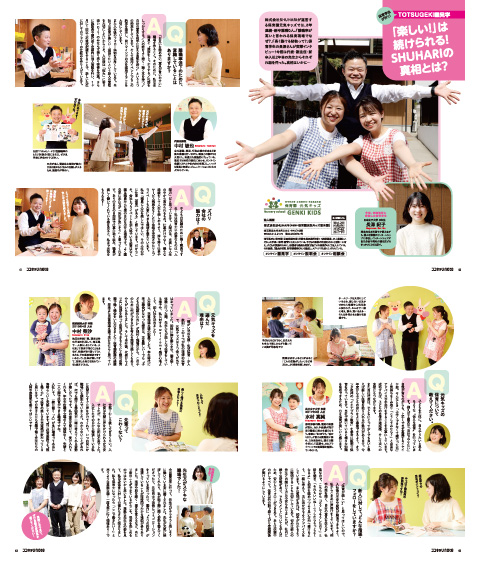参考:メルマガバックナンバー 2020.07.9配信
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密 vol.4「理念を実現化する強力なツール」
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密
「パワフルな理念を現実化するシンプルだけど強力なツールとは!?」
こんにちは。
株式会社SHUHARI 中村 敏也です。
前回は、パワフルな理念の作り方についてご紹介しました。
でも、素敵な理念があっても、なんだか口だけだなって感じることありませんか?
例えば、CMなどで良いこと言ってるけど、実際は不祥事を起こしてしまう会社とか…
子どもたち、保護者、働く先生たちがみんな笑顔が一番!
そんな保育園です!!
って言っているのに、子どもたちは軍隊のような保育を受け、
保護者へはしっかりした説明のないまま一方的な情報を突きつけ、
先生は偉い人の目ばかり気にしているような…
とても素敵な理念ができたとしても、保育園がその理念に向かって進んていくという空気感がないとなんの意味もないですよね。
この空気感こそが、「文化」です。
良い保育園には、どこでもこの良い空気感が流れいます。
では、この文化、どうやって出来て、どうやって維持していくのでしょうか?
その鍵が「シンプルなルール」です。
元気キッズの事例でご説明しますね。
保育園 元気キッズは、「子どもたちが最高の笑顔になる場所」という想いのもとスタートしました。
しかし、立ち上げ当初、保育に関して素人の私は、
周りより少し声が大きくリーダーシップがある職員についつい頼ってしまい、
結果、その人が絶対正義の施設ができあがってしまいました。
もちろん「子どもたちのため」という信念は、そのリーダー保育士も僕も一緒。
でもなんだか誰も意見が言えない、雰囲気の硬直した組織になっていったのです。
そして気がつけば、離職率が3割を超えていました。
「あー。こんな保育園にしたかったわけではないのに」
「みんなが笑顔になる場所にしたいのに」
私自身、どんどんどんどん元気がなくなり、ほぼ鬱状態になりました。
当時、暗い部屋の中で、回転チェアの上に膝を抱えながら体育座りをして、
くるくる回っていた僕を見た妻は、そっとドアを閉めて「見なかったことにした」
と後で笑い話にしてくれました。
それくらいヤバい状態に!
みなさんも経験ないでしょうか?
きっとあると思います!
デスノートのLみたいな感じになった時が(笑)
どん底の中、私は自問自答を繰り返しました。
どんな保育園にしたい?
どんな先生たちと仕事をしたい?
一体何をしたいのだ?
と。
その結果、得た答えは、
「すべては子どもたちの笑顔のために行動すべし!」ということでした。
子どもたちを最高の笑顔にするためには、まずは先生たちが笑顔で働く場所が必要だ。
お互いが尊敬しあい、支え合い、誰にもで意見がいえる風通しの良い職場が必要だと。
しかし、このような長い説明を先生たちにしても、
「そんなこと誰もが望んでますよー。でもなかなか ないよね」って雰囲気が蔓延していました。
なかなか現場が変わらない。
だったら、そんな組織になるために、行動指針を作ってしまえ!とできたのが、
元気キッズの4つの約束でした。
1.あいさつ
2.礼節
3.人の話を聞く・聞く耳を持つ
4.自分の意見をいう勇気を持つ・わかるように説明する
という誰でもわかるシンプルなルールを設定。
さらに個人面談を強化し、何度何度もこの4つの約束を1人ずつに話していきました。
するとどうでしょう(ビフォーアフターのテーマに乗せて♪)
4つの約束に共感した職員がどんどん増えていき、現場に優しい風が吹き始めました。
そして、実習で施設に来てた学生から、最終日に
「元気キッズはありがとうが溢れています!」
という言葉をもらうことができました。
4つのルールが文化を作り、維持し、理念を体現していることを実感した瞬間でした。
このシンプルなルールは、かなり強力なツールになります。
ぜひ、ご自身の保育園でも必要不可欠な行動指針を作り、みんなで共有して見てください。
きっと望ましい行動を自然ととる職員ばかりになることでしょう。
次回は
理念と文化とルールが機能しはじめて起きた奇跡の数々について配信予定です。
——————————————————————
株式会社SHUHARI
保育園元気キッズ 代表 中村敏也
発行:株式会社SHUHARI
※ 当メールマガジンの内容の無断複製・転載・使用を固く禁じます。
Copyright 2007 SHUHARI Corporation. All Rights Reserved.
中村敏也のメールマガジンでは
・保育・児童発達支援の経営のためになる情報
・オンラインセミナーのご案内(メルマガ読者限定案内あり)
・講演会のご案内
などをお送りしています。
困っている保育所の足元を見た高額な人材紹介会社に頼らず、自力で採用できる力を、すべての保育所が持つことができれば、より良い保育環境が広がるはずです。
子どもたち、保護者、保育士にとって、とても幸せな世界になることを願って、少しでもお力になれれば幸いです。
※メールが届かない場合、携帯メールの受信設定、迷惑メールの設定などをご確認ください。
@shuhari.bizからのメールを受信できるようにしておいてください。
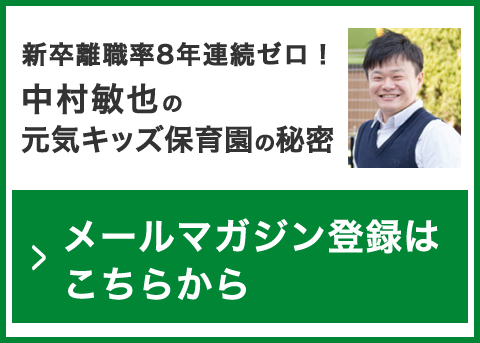
2020年8月26日
中村敏也のメールマガジンでは
・保育・児童発達支援の経営のためになる情報
・オンラインセミナーのご案内(メルマガ読者限定案内あり)
・講演会のご案内
などをお送りしています。
困っている保育所の足元を見た高額な人材紹介会社に頼らず、自力で採用できる力を、すべての保育所が持つことができれば、より良い保育環境が広がるはずです。
子どもたち、保護者、保育士にとって、とても幸せな世界になることを願って、少しでもお力になれれば幸いです。
※メールが届かない場合、携帯メールの受信設定、迷惑メールの設定などをご確認ください。
@mm.genki-kids.netからのメールを受信できるようにしておいてください。
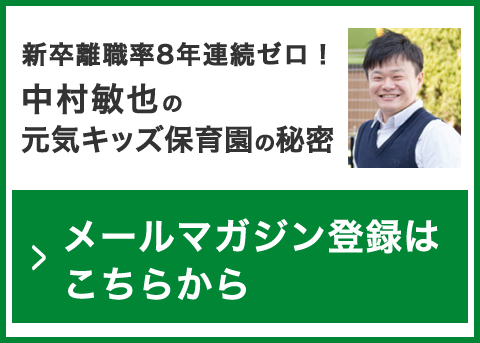
参考:メルマガバックナンバー 2020.07.2 配信
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密 vol.3「パワフルな理念ができるまで」
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密
「パワフルな理念ができるまで」
こんにちは。
株式会社SHUHARI 中村 敏也です。
私は、セミナーでお話する際に、常に「経営には理念が大切です」と繰り返しています。
理念経営、理念に基づいた行動、意思決定などなど。
では「理念」とはそもそもなんでしょうか?
認可保育園は、個人事業者には認められず、社会福祉法人、NPO法人、株式会社などの法人が行います。
法人とは、人間とまったく別の存在である法律上人格が認められたもののこと。
つまり、人格があるということです。
人間にはいろいろなタイプ、様々な考えをもつ人がいるように、
目的をもって設立された法人にも、それぞれの考え方、くせ、性格みたいなものが不思議と出てきます。
大概、法人の性格は、代表の考えを表したものになるし、創業者の考えを大きく反映したものになります。
その性格を言葉に表したものが「理念」です。
そして、理念は指針です。
理念を持つと、理念をよりどころに、組織が向かう方向、職員たちの行動方針など、選択をする際に迷わずに進むことができます。
では、理念はどのように作られるのでしょうか?
大きく分けて2つ必要な要素があります。
1.印象に残る言葉
みなさんの保育所も、きっと保育理念などが策定されていると思います。
でもそれは、本当にやりたいこと、実現したいという想いが理念に込められているでしょうか?
それとも、どこか借りものの言葉が使われていたりしませんか?
実は、恥ずかしながら私自身も自分の思いを表してはいるが、
なんとなく心地がいい、安易な言葉を使って理念を作っていました。
以前の理念はこちら。
「子供達の未来の基礎力を育む!」
「全ての場所で子どもたちが最高の笑顔になれる社会」
まぁ、悪くないけども、なんだかどこにでもありそうな言葉という印象。
会社の理念なのか、保護者に向けた保育の理念なのかはっきり定めていなかったため、
誰に伝えたいのかぼやけていて、はっきり言って印象に残らないなと。
会社の理念は、働く人の寄りどころにならなければなりません。
働く人たちに覚えてもらい、自分の言葉であるかのように自身に染み込ませてもらわなければなりません。
したがって、インパクトがある言葉が必要になるのです。
2.代表自ら紡ぎ出す言葉
理念は法人の性格です。
そうしますと、どこかで聞いたことがある、聞こえの良い言葉を理念として掲げても、
誰も本気でその理念に共感したり、指針にしていこうとは思いません。
ではどうすれば良いか?
代表自らが言葉にするしかないのです!
自分の体験を振り返り、自分のやりたいことを明確にし、
何をこの法人を通じて実現していきたいかを絞り出し……
ひねり出し切った先に、本当の心の言葉が生まれてきます。
でも、これは一人でやるのは、とてもとても難しいことです。
思いを言葉に表すのは、言語化力、コピーライティング力も必要になります。
「SHUHARIの事業理念の作成」
元々のSHUHARIの理念については、すでにお話しした通りです。
本気で思っていたことなので、ある程度は伝わっていたと思いますが、
印象に残るかというと別の話になります。
そこへ、新型感染症の波が押し寄せてきました。
コロナ禍の中、このままで良いのか色々と考えました。
職員のこと、会社のこと、何より子ども達のこと。
みなさんもきっと色々と悩み、苦しみ、リーダーとしてどうすれば良いのか、もがき苦しんだことでしょう。
私は、大きな時代の変化のために、指針となりうるバージョンアップした理念が必要だと思い立ちました。
そしてしっかりと作るために言葉のプロに相談し、作成の依頼をしました。
そこで、多くの言葉のやりとりがあった後にできあがった法人の理念がこちらです。
——————-
しなやかに、ひたむきに
SHUHARI
時代の変化に対応するしなやかさと、
本質的な価値を守るひたむきさを大切にしながら、
家族にとって安心安全な環境を創造し、
かかわるすべての人の笑顔と豊かさを増やします。
——————-
自画自賛ですが、言葉に強い意思と、惹きつけられる魅力がとても増したと思います。
決して一人では出てこなかったと思いますが、
すべて私自身から出てきた言葉で構成されています。
このように、時代の変化や、組織の成長とともに、理念も変化して良いのです。
ぜひ、取り巻く状況が変わった、今の組織の目指すべき目標が替わった際は、
思い切って理念を作り替えることをおすすめいたします。
——————————————————————
株式会社SHUHARI
保育園元気キッズ 代表 中村敏也
発行:株式会社SHUHARI
※ 当メールマガジンの内容の無断複製・転載・使用を固く禁じます。
Copyright 2007 SHUHARI Corporation. All Rights Reserved.
中村敏也のメールマガジンでは
・保育・児童発達支援の経営のためになる情報
・オンラインセミナーのご案内(メルマガ読者限定案内あり)
・講演会のご案内
などをお送りしています。
困っている保育所の足元を見た高額な人材紹介会社に頼らず、自力で採用できる力を、すべての保育所が持つことができれば、より良い保育環境が広がるはずです。
子どもたち、保護者、保育士にとって、とても幸せな世界になることを願って、少しでもお力になれれば幸いです。
※メールが届かない場合、携帯メールの受信設定、迷惑メールの設定などをご確認ください。
@shuhari.bizからのメールを受信できるようにしておいてください。
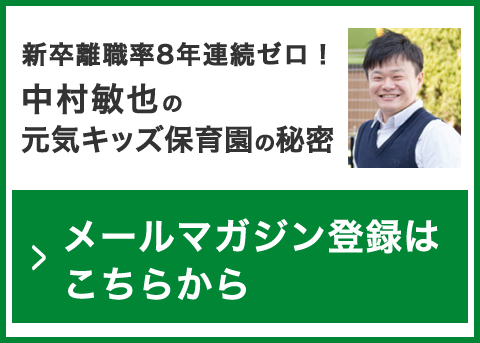
2020年8月20日
保育専門の就職情報誌ココキャリnote 2020年7月号の特集記事
「保育学生が行く!TOTSUGEKI園見学」
に保育園 元気キッズが取材され掲載されました。
「楽しい!」は続けられる!
株式会社SHUHARIが運営する保育園 元気キッズの真相とは?
日本女子大学3年生の保育学生が体験保育に参加し取材されました。
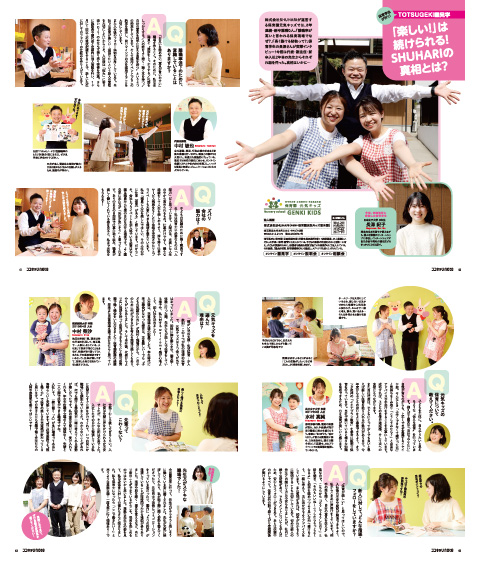
↓拡大画像はこちら
ココキャリnote 2020年7月号特集 掲載記事PDF(3.1MB)
https://kodomoo.org/pdf/cococari202007.pdf
2020年8月4日
参考:メルマガバックナンバー 2020.06.25配信
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密 vol.2「「変化できる力」の話」
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密
来年還暦を迎える施設長の「変化できる力」の話
こんにちは。
株式会社SHUHARI 中村 敏也です。
今回は、元気キッズに入社し約10年の、ある保育士の話です。
彼女は、元気キッズの何もない家庭保育室時代に、私の想いに共感してくれて、公立の保育園から転職。
4年前(平成28年4月)の元気キッズ初の認可保育園の立ち上げから、
認可保育所の施設長になり、現在にいたります。
来年還暦を迎える彼女は、もはや「元気キッズの母」といった存在ですね。。
職員からも子どもたちからも慕われている彼女も、
入社してから今まで、いくつもの壁がありました。
彼女を言い表すと、スパっとした気持ちのよい性格で、好き嫌いがはっきりしている義理人情に熱いタイプ。
入社時の保育の傾向は、先生主導型。
「先生の言うことを聞いて、言われたことをしっかりやることが善」という価値観を捨てきれずにいました。
ほとんどの職員は彼女を尊敬しついていけるが、まれに、ついていけないという職員も。
みなさんの保育所にもきっといると思います。
昔ながらの価値観をもって、良いと思って行動しているが、世代間の違いでなんだかチグハグしてきている年配の職員が。
それでも、家庭保育室時代は、とてもうまくチーム運営ができていたのですが、
認可保育所になり、マネジメントする人数が増えたとたんに、問題が出てきました。
新卒の職員は、肝っ玉母さんである彼女の愛につつまれて、しっかり育っていくものの、
中途入所職員のなかには戸惑い、やがてやめていく人が出てきたのです。
そのようなことが続くと、次第に園内の雰囲気が悪くなり、みんなが周りを気にしながら保育をするように……。
彼女はとてもとても悩みました。
「子どもたちの笑顔のために保育をしたいのに……」
「人間関係でつまずいて、保育に集中できないなんて……」と
そして、私との個人面談を何度も何度も重ねていきました。
面談では、いくつかの問題点が職員から上がっていることを正直に伝えました。
「子どもへの言葉が強い」
「昔からの職員ばかりと相談して、勝手にものごとが決まっていく」
「冷たい」など
彼女は、大変ショックだったと思います。
想いが伝わらない悔しさや、自分の至らなさに涙を流しながらの面談は続きました。
私は、「元気キッズの4つの約束(挨拶、礼節、人の話を聞く、自分の意見を伝える)を体現してほしい」
「とにかくやってみて、ダメだったら元に戻せば良いだけだよ」と伝えました。
普通に考えると、ベテラン保育士の彼女が、自分より20歳も年下の私から指摘され、
「今のやり方ではダメ」とノーを突きつけられたら、きっとやめてしまうか、逆切れしてしまったり、
「みんなが理解しないのが悪い、私は正しい」と自分の意見に固執してしまっても当然のように思います。
しかし、彼女は違いました。
「私、変わります!」と、面談の最後に宣言。
翌日から、子ども主体の保育の実現のため、働く職員の考えを吸い上げるため、積極的にコミュニケーションを開始しました。
そして、元気キッズの4つの約束を自ら実行していきました。
すると、重たかった現場に徐々に変化がおき、とてもすがすがしい、本来の彼女のような雰囲気の施設になっていきました。
認可保育所2年目のときにはじめて実習生を受入れ、実習最終日に言われた言葉が今でも忘れられません。
「元気キッズには、ありがとうが溢れています!」と。
たった1年で、元気キッズらしさである「挨拶、礼節」が浸透していました。
そして現在5年目、先日6月23日に彼女と職員たちの目標シートの評価のためのミーティングを行いました。
彼女から発せられる言葉は、すべての職員に対して、ポジティブな内容でした。
「率先して片付けや掃除をする先生ばかりで、私がやっているとすぐに仕事を奪われてしまうのです」
「縦割りの自由保育のミーティングは、はじめは私がファシリテーションしてたのですが、
いまでは先生たちが率先してやっていて、ちょっとついていけないくらいの濃い内容を話しているんです!」
「指示待ちだった中途入社の先生が、去年の年長の担任を経て、自信がみなぎっていて、すごく積極的に提案をするようになったんです」
などなど。
先生たちに訪れた数々のポジティブな変化。
でもこれは、施設長である彼女の変化が起こしたこと。
そのことを彼女に伝えました。
「いえいえ、自分の力ではないです。みんなが本当にすごいから」と。
還暦が近い年齢でも、決して奢ることなく、自ら変化をしつづける彼女は、きっとこれからも職員たちを導き、子どもたちの笑顔のために邁進してくれることでしょう。
このように、園の施設長が、その園の性格を決め、雰囲気をつくります。
人こそ宝です。
ぜひ、自分の理想の保育を実現するために、理念をつくり上げ、共感する仲間を集まってもらいましょう!
次回は、元気キッズの理念を形にしていった話を配信予定です。
——————————————————————
株式会社SHUHARI
保育園元気キッズ 代表 中村敏也
発行:株式会社SHUHARI
※ 当メールマガジンの内容の無断複製・転載・使用を固く禁じます。
Copyright 2007 SHUHARI Corporation. All Rights Reserved.
中村敏也のメールマガジンでは
・保育・児童発達支援の経営のためになる情報
・オンラインセミナーのご案内(メルマガ読者限定案内あり)
・講演会のご案内
などをお送りしています。
困っている保育所の足元を見た高額な人材紹介会社に頼らず、自力で採用できる力を、すべての保育所が持つことができれば、より良い保育環境が広がるはずです。
子どもたち、保護者、保育士にとって、とても幸せな世界になることを願って、少しでもお力になれれば幸いです。
※メールが届かない場合、携帯メールの受信設定、迷惑メールの設定などをご確認ください。
@shuhari.bizからのメールを受信できるようにしておいてください。
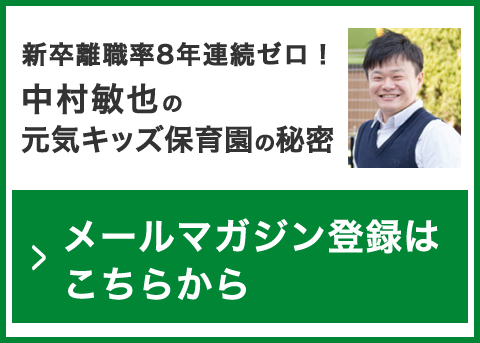
2020年7月11日
中村敏也のメールマガジンでは
・保育・児童発達支援の経営のためになる情報
・オンラインセミナーのご案内
・講演会のご案内
などをお送りします。
困っている保育所の足元を見た高額な人材紹介会社に頼らず、自力で採用できる力を、すべての保育所が持つことができれば、より良い保育環境が広がるはずです。
子どもたち、保護者、保育士にとって、とても幸せな世界になることを願って、少しでもお力になれれば幸いです。
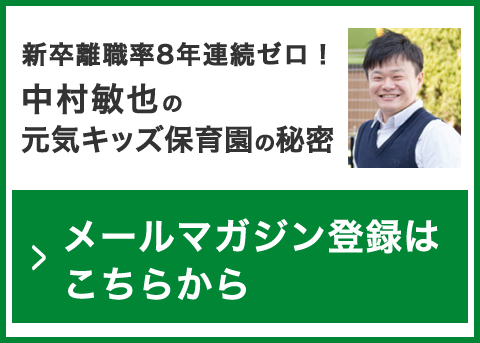
参考:メルマガバックナンバー
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密 vol.1「100%パクられた採用コピー」
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密
こんにちは。
メールマガジン「中村敏也の元気キッズ保育園の秘密」にご登録ありがとうございます。
株式会社SHUHARI 中村 敏也です。
今回は、なぜこのようなメールマガジンを始めたのかをお伝えいたします。
それは「保育業界なめんなよ!」という怒りが、僕を動かしているから。
私たち元気キッズは、離職率が低く、採用もうまくいっている保育園の一つです。
自慢のようで恐縮ですが、採用に対しても、雇用維持に対しても、全力で改善を繰り返してきた結果だという思いがあります。
おかげで理想の職員に囲まれていますが、毎年新規開園をしているため、一定の職員を採用しつづけなければなりません。
毎年頭を抱えながら、様々な試行錯誤をしています。
その中でも最近力を入れているのが、インディード。
クリック単価方式の求人サイトなので、非常に管理がしやすく、使い勝手も良い。
期間を決めて、内容を少しづつ変えて、求人広告の効果が少しでも高まるよう工夫しています。
いわゆるABテストを行っているのです。
そんなある日、ふとインディードの広告を眺めていたら、見覚えのある求人に目が止まりました。
住所、給与内容、勤務形態、職務内容が、わが社と同じ。
「あれ? どこかでみたことあると思ったら、先月出していた弊社の求人内容だ!」
とおどろいてさらに読み進めると、もっと驚愕な事実が!
施設名が「保育園元気キッズ新座池田園」と記載されているのです。
その園の広告はすでに違う内容で出しているはずなので、おかしいな?と困惑して読み進めると、
「運営 株式会社XXX」と、弊社とは全く関係のない会社の名前で募集が行われているではありませんか!!!!
キャッチからコピーまで丸パクリの求人情報を、弊社の園名を語って、インディードに掲載している!!
なぜ、その会社はそんなことをするのか?
それは、その株式会社XXXが、人材紹介会社だったからなのです!!!
その人材紹介会社は、私たちが募集しているエリアで、私たちの考え出したコピーを使った求人広告を、私たちの名前入りで堂々と出していました。
弊社に直接応募させるのでなく、その会社を通じて応募させ、高額な紹介料をとるための、とてもとても安易で姑息なマーケティングをしていいました……
ここで本当に名前を出したいほど、いまだに怒りが収まりません。
ちなみにその会社には、即刻連絡、広告の停止をさせ、二度と弊社の広告を使わない旨の誓約書を書かせました。
人材難で困っている保育業界に、このような卑怯なことを平気で行う会社が、存在するのです。
そして、大切な保育の委託料を平然と奪っていく世界は、全く健全ではないと思います。
まして福祉業界は、ITやマーケティングなどビジネス面で強い施設はあまりないのが現状です。
小手先のマーケティングで、人の褌でお金を稼いでいく人材紹介会社がのさばっていては、健全な保育環境は保てません。
保育業界は、あしき人材紹介会社、あしき保育求人サービス会社と決別しないといけないのです。
大切な保育の委託費を、採用のためばかりに浪費するのではなく、
保育者、そして、子どもたちのために使いたい!!
というのが、全国の園長先生の切なる思いだと思います。
そこで、何もないところから試行錯誤でできあがった元気キッズのモデルが、
全国の保育所運営にお悩みの園長先生たちの少しでもヒントになるではないかと思い、
セミナーを開催したり、メルマガを発行したりすることにいたしました。
これから、毎回、保育園経営のヒントになるようなことを記事にしていきますので、どうぞお楽しみに。
ご質問やご相談も受付けていますので、お気軽にメールいただければと思います。
最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
理想の保育園経営で、子どもたちの笑顔を一緒に増やしていきましょう!
——————————————————————
株式会社SHUHARI
保育園元気キッズ 代表 中村敏也
発行:株式会社SHUHARI
※ 当メールマガジンの内容の無断複製・転載・使用を固く禁じます。
Copyright 2007 SHUHARI Corporation. All Rights Reserved.
2020年6月23日