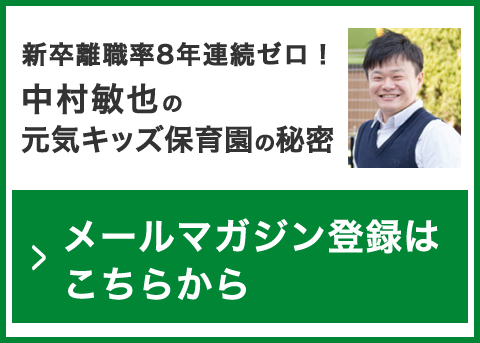参考:メルマガバックナンバー 2020.09.16 配信
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密 vol.9 地域社会を変える保育園への道4
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密
地域社会を変える保育園への道4
多店舗展開する時の心構え編
こんにちは。
株式会社SHUHARI 中村敏也です。
地域社会を変える保育園への道その4
前回、開所の落ち込みからV字回復を果たした中村青年。
次の一歩として、2施設目を早期に立ち上げたいと考えていました。
実は創業前から、保育園経営、特に雇用の環境を整えるためには、
経営基盤を安定させねばならないと、早期に3施設までやると決めていました。
認可保育所と比べたら家庭保育室1施設だけでは収益力が雲泥の差のため、
まずは3施設までは増やそうと考えていたのです。
● 3年で3施設開所の目標
よく自己啓発本などでは「やるべきことリスト」を作り、
それに向かって努力をつづけると不思議なことが起きるもの
と書かれていたりします。
とても怪しい感じですよね。
思えば叶うって。
私もそんなことがあるのかな? でもそうであって欲しいなと思い、
創業計画のA4の紙にやりたいことをマインドマップで全て書き出してみました。
すると…
本当に不思議なことが起ききたのです。
しかも1つや2つでないのがすごいところ。
■ 2施設目の開所
1施設目が軌道にのり、園児も定員いっぱいになり、良い波にのれて勢いのある時のことです。
そろそろ職員を増やそうと求人情報を出した際、面接にきてくれた人が、
驚くべき相談を持ちかけてきたのです。
「今勤めている保育所が閉所するので、助けてくれませんか?」と。
「そんな話あるの?」と半信半疑で話を聞きにいくと、
商業施設内の保育所で、思ったより人が集まらないので撤退したいとのことでした。
職員も施設も全て引き渡すのでやって欲しいという提案が、舞いこんできたのです!
お話をいただいたこの施設は、立地がとても悪かったのですが、
マーケティングの力を信じていた中村青年は、
保育の仕組みはしっかりあるから事業継続はできると判断し、
すぐに請け負うことを決めました。
ほとんどお金をかけずに、人も、施設も、他園のノウハウまで取得することができたのです。
本当にびっくりすることが起きるものです。
2施設目となるこの保育所は積極的な告知活動をして、
すぐに単月度での黒字化に成功しました!!
しかし、やはりこの施設はとても立地が悪く、広告の努力がとても必要な場所でした。
1年が終わるころに「なかなかきついな」と思っていたところ、
駅前にまるで保育園のために建てられたのではないかという煉瓦造りの可愛い建物が貸し出しになっていたのです。
すぐに不動産屋に連絡を入れると、ちょうど今日開示したばかりの物件だと!
なんという幸運!
そして、もっと奇跡が。
なんとこの物件のオーナーが、母方の親戚筋の方だったのです!!
とっても優しい大家さんで、信頼していただき、話はとんとん拍子に進みました。
これはおばあちゃんのお導きなのかかもしれないと、純朴な中村青年は即決で契約。
無事移転できました。
駅近でとても可愛らしいテナントの保育施設は、すぐに軌道にのり、今でも安定した運営をしております。
■ 3施設目の開所
そんなドタバタした2年目が終わる頃、
今度は自治体から「このエリアで保育園を運営してほしい」という依頼がありました。
フットワークが軽いことが唯一の武器の中村青年は、早速、物件調査。
なかなか良い物件がでないエリアなのですが、こちらもスムーズに物件を見つけ契約。
職員もすぐに集まり、3年目で3施設目の開所ができました。
3つ目の施設を開所したあと、見直した創業当初のマインドマップメモには、
3年で3施設の開所という目標がかき入れてあったのでした…
今、振り返ってもたくさんの人からの助けがあり、幸運に恵まれた3年間でした。
快進撃を続ける中村青年ですが、
実は少し前から気づいていたけど、目をつぶっていた問題が、
その頃から、大きく大きくのしかかってきたのでした…
次回は、「経営ってやっぱり人だよ! 理念だよ!」ってお話です。
【再掲】
いよいよ来週、中村敏也の保育園経営セミナーを開催します!
大きな時代の変化の中、保育業界においても、漠然とした不安があると思います。
ゼロから保育所を立ち上げて、地域でダントツに必要とされる保育所、児童発達支援事業所、
さらには様々な福祉サービスを作ってきた中村とともに、これからの保育のことを考えてみませんか?
当日は、自園の強みを発見するワークも行いますよ。
◎9/23(水)オンライン無料セミナー
「自園の保育の強みを見出し、発見するワークショップ」セミナー
開催日:2020年 9月 23日 (水)、13:00~15:00
開催地:オンラインzoom(お申し込みの方にメールでお知らせいたします)
参加費:無料
定員:20名程度(残席わずか)
タイムテーブル:
13:00~13:45 第一部「これから求められる保育所像」
13:45~14:15 第二部「強みを発見するワーク」
14:15~15:00 質疑応答
◎申込期限:9月19日土曜日20時まで
残席わずかです。
少しでも興味がありましたらぜひご参加ください。
参加希望の方はこちらをクリック↓
【※注】オンラインセミナーは終了しております。
メルマガ読者の皆様には8/27に号外でセミナー案内をお送りいたしました。
——————————————————————
株式会社SHUHARI
保育園元気キッズ 代表 中村敏也
発行:株式会社SHUHARI
※ 当メールマガジンの内容の無断複製・転載・使用を固く禁じます。
Copyright 2007 SHUHARI Corporation. All Rights Reserved.
中村敏也のメールマガジンでは
・保育・児童発達支援の経営のためになる情報
・オンラインセミナーのご案内(メルマガ読者限定案内あり)
・講演会のご案内
などをお送りしています。
困っている保育所の足元を見た高額な人材紹介会社に頼らず、自力で採用できる力を、すべての保育所が持つことができれば、より良い保育環境が広がるはずです。
子どもたち、保護者、保育士にとって、とても幸せな世界になることを願って、少しでもお力になれれば幸いです。
※メールが届かない場合、携帯メールの受信設定、迷惑メールの設定などをご確認ください。
@shuhari.bizからのメールを受信できるようにしておいてください。
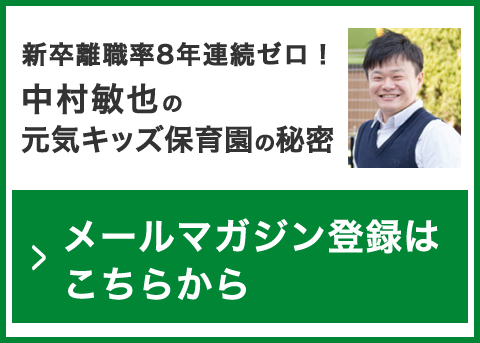
2020年10月1日
参考:メルマガバックナンバー 2020.08.20 配信
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密 vol.8 地域社会を変える保育園への道3
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密
地域社会を変える保育園への道3
まさかの入所児童1名!!から3ヶ月で黒字化した方法
こんにちは。
株式会社SHUHARI 中村敏也です。
地域社会を変える保育園への道その3です。
前回は、開所までの奮闘記をお伝えしました。
今回は、「世の中そんなに甘くない編」です。
開園イベントに多くの方にお越しいただき、心の中でガッツポーズをしていた中村青年。
定員23名の保育所に、63名のイベント参加者。
これはどう考えたって、すぐに定員の半分くらいは埋まるんじゃない?
なんてほくそ笑んでいたのでした。
しかし、イベント終了後、アンケートを集計していくと、
驚きの事実がわかってきたのです。
肝心の、
即入園希望の欄への YES の丸が見つからない。
63枚のアンケートをくまなく読んでも、入園希望がない。
ゼロ、零、、、、。。。。
10度見くらい見返しましたが、すぐの入園希望者がありませんでした。
イベント最中のほくそ笑んでいた笑顔が、どんどん無表情になっていったのです。
いや、青ざめていったのでした。
結局開所日までに、入園が確定していたのは、保険屋さんから紹介を受けた1児童のみという結果に・・・・・・。
何が間違っていたのだ?
63名中、1名の入園なんて、少なすぎる!!
これからどうすればいいんだ!
開所までの同じ労力を22回しなきゃならないの?
そんな悠長なことをしていてはお金がすぐに枯渇する!!
恐怖と絶望感で頭の中が真っ白になりました。
あのほくそ笑んでいた自分に腹が立つ。情けない・・・。
しかし、ここで心が折れる中村青年ではなかったのでした。
自分ができることはすべてやってやろうじゃないか! と心を奮い立たせ、
自分にあるのは「若さ」と「マーケティングの知識」のみと再度自覚。
しっかり振り返って対策を練ろうと、まずは状況の分析をした結果、
敗因がいくつか見えてきました。
1つ目は、誇大広告
「楽しい幼児教育の保育園」というテーマをイベントで押していたのにも関わらず、リトミックと製作を少しやる程度のイベント内容。
期待値を煽りすぎたため、信頼獲得にいたらなかった。
2つ目は、時期
9月の開所のタイミングで、すぐに入りたいという方が少なく、
やはり4月などの節目の方が保育園を探している方が多いということ。
これはわかっていましたが、やっぱりそうかという。
希望的観測は通用しないと身をもって知りました。
3つ目は、アプローチ不足
イベント前に集まったリストへのアプローチが告知案内のみの1回のみで、全くの手付かずで放置してました。
もっと活用せねばならないと反省。
ここからはマーケティングの力をフルに活用していきました。
お金がないために、大きなプロモーションが打てない。
リストをしっかり活用するしかありませんでした。
そこで、来ていただいたご家庭に向けて、
イベントから3日後に届くように、お礼のお手紙を
1週間後に、当日の写真を加工し、親子が写っている絵葉書を作成して送付。
そして、3週間後に、イベントの告知とともに、入園金無料、一時保育登録料、2時間無料券を発送。
他に若さを活用した公園などでの声かけ、イベント案内チラシのポスティングを実行しました。
すると、徐々に利用希望者が集まってきて
月極め保育での児童が
1ヶ月後には7名
2ヶ月後には9名
3ヶ月目にいは11名と、採算ラインの10名を超えることができたのです。
また一時保育の利用者も増えて、開所から3ヶ月でキャッシュフローの黒字化を達成しました。
開所してからの3ヶ月間は、本当にお金がなくなる恐怖で、毎日必死でした。
もし園児が増えなければ、借金だけが残り、また会社勤めだなと・・・。
2ヶ月目に入ったときには、夢に出てきたおばあちゃんに励まされながら、
どうにか歯を食いしばり、職員と力を合わせて乗り切ることができました。
今の保育所事情では考えられないくらい、大変な時期でした。
今思えば、そんなに心配しなくたって大丈夫だったのにって思えますし、
まだまだぜんぜん努力が足りないよ、中村青年って思いますが、
当時は、悲壮感の塊で、本当にちっちゃい人間だったと思います・・・。
自分なりに大きな波を乗り切った中村青年は、次は多店舗展開へ突き進むのでした。
******
中村敏也の保育経営オンラインセミナーのお知らせ
来月23日、オンラインにて保育経営セミナーを開催いたします。
テーマは、
「待機児童問題がひと段落した今、地域で選ばれる保育園になろう」
待機児童問題がひと段落した今、都内でも認可保育園に空きが出てきました。
これからの時代は、保護者、保育士から選ばれる保育園にならなければ、
安定した園運営ができなくなります。
そんな不安を少しでも解消できるような各園のロードマップを作る
ヒントをお伝えいたします。
■中村敏也の保育経営オンラインセミナー
「待機児童問題がひと段落した今、地域で選ばれる保育園になって安定運営を実現しよう」
日時:令和2年9月23日(水)13:00~14:00
場所:オンライン zoom(お申し込みいただいた方にご連絡させていただきます)
参加費:無料
定員:20名程度
申込方法は来週のメルマガでご連絡いたします。
ご興味がある方がいらっしゃいましたらぜひ参加をご検討ください。
【※注】オンラインセミナーは終了しております。
——————————————————————
株式会社SHUHARI
保育園元気キッズ 代表 中村敏也
発行:株式会社SHUHARI
※ 当メールマガジンの内容の無断複製・転載・使用を固く禁じます。
Copyright 2007 SHUHARI Corporation. All Rights Reserved.
中村敏也のメールマガジンでは
・保育・児童発達支援の経営のためになる情報
・オンラインセミナーのご案内(メルマガ読者限定案内あり)
・講演会のご案内
などをお送りしています。
困っている保育所の足元を見た高額な人材紹介会社に頼らず、自力で採用できる力を、すべての保育所が持つことができれば、より良い保育環境が広がるはずです。
子どもたち、保護者、保育士にとって、とても幸せな世界になることを願って、少しでもお力になれれば幸いです。
※メールが届かない場合、携帯メールの受信設定、迷惑メールの設定などをご確認ください。
@shuhari.bizからのメールを受信できるようにしておいてください。
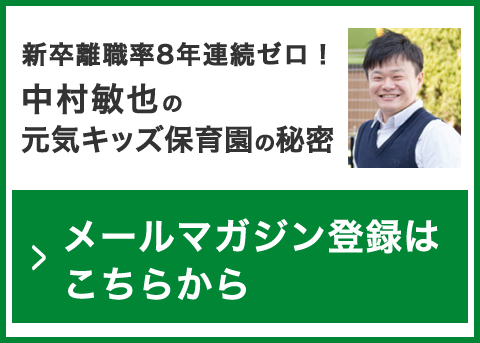
2020年9月24日
参考:メルマガバックナンバー 2020.08.05 配信
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密 vol.7 地域社会を変える保育園への道2
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密
地域社会を変える保育園への道2・開所準備
こんにちは。
株式会社SHUHARI 中村 敏也です。
地域社会を変える保育園への道 その2です。
さて、前回、保育所の開所を決意した中村青年は、
事業をするには
1.資金 2.場所 3.人
この3つが必要というのは、独立開業の本に書いてあるのでなんとなく知っていました。
■運の良さもあって3つの要素は揃った!
1.資金
まずは元手が必要です。
激務の会社勤めのおかげで、お金を使う時間がなかったために、3年間である程度の貯蓄ができたのと、
ネットバブルの影響でたまたま株式投資がうまくいったことで、500万円の自己資金がありました。
さらに、素人ながらもがんばって作った資金計画をもって
国民生活金融公庫(現在の日本政策金融公庫)にお願いに上がり、
500万円の融資をつけることができ、合計1000万円の資金を作ることができました。
26歳にしては、我ながらよく頑張ったな(笑)・・・と思います。
2.場所(物件)
物件は、会社に在籍中、休日に地元の不動産屋を尋ねまわりました。
自宅でもインターネットを駆使して物件探しに集中。
3か月ほど探していると、駅から近くて、家賃もほどほどのよい物件が見つかりました。
しかも、オーナーが遠い親戚筋の方で、ご縁を感じました。
ご先祖様に感謝。
3.人(繋がり・人材)
現在は、保育士不足で大変な採用難ですが、2006年当時はそれほど難しいわけではなく、
タウン誌とハローワークのみで数名面接できました。
そのうち社員2名パート2名の計4名の方とご縁がつながり、立ち上げメンバーになってもらいました。
前向きでやさしい良い方たちばかりに集まってもらえて、本当に良かった。
いまだに当時のことを思い出すと、奇跡的だったなと思います。
物件が見つかり、施工業者も決まりました。
この施工会社とは実はいまでもつながっております。
本当にご縁って大切ですね。
保育園 元気キッズのキャラクターのパンダは、
小学校からの幼馴染で当時はまだ学生であった高橋理子さん
( https://takahashihiroko.jp/ )にお願いしデザインしていただきました。
しかも御礼はお寿司をおごっただけで快諾してくれて、本当にありがたかったです。
彼女はいまでは世界的に活躍する日本のトップクリエイターなので、
なんと恐れ多いことをしたのかと反省しています。
■利用者集めに苦労した広告活動
物件契約、内装工事費、保育備品、人件費などで、湯水のようになくなる資金に
怖気付きつつも、成功だけを信じて進む日々でした。
まずは保育所の利用者がいなければ事業は存続できないということで、
マーケティングがとても重要です。
といっても、すでに結構なお金をつかってしまったため、
広告費にはあまりお金をかけられない状況でした。
そこで行ったのが、
1.ポスティング
2.DM
3.直接の声がけ
1.ポスティング
ホームページと、チラシを作成し、
お金がないので自らポスティングをする毎日でした。
9月開所だったので、ちょうど今頃、7月末から8月中旬にかけて行いました。
日中は暑いし、人目があるので、日中の作業が終わった後に毎晩行いました。
1日に1000部配布し、10日続けて1人で1万枚を配布。
正直、もう二度とやりたくない・・・笑
2.DM(ダイレクトメール)
いまでは嘘のような話ですが、当時は役所へいけば住民台帳を見ることができたのです。
そこで、500世帯ほどの情報を調べ、個別にダイレクトメールを作成し発送しました。
個人情報がだだもれの世界に、罪悪感を感じながらも、
マーケティングとは「必要としている方へ必要な情報をとどける行為」なので、
とても良いことをしているのだと勝手に思い込み実行していました。
3.直接の声がけ
そして、もっとも苦手だったのが、駅前や公園でのチラシ配りです。
ほとんどの方には受け取ってもらえないけれど、たまに笑顔で受け取ってくれる方がいたり、
「がんばってね」と声を掛けてくださる方もいて、厳しさとやさしさの両方を経験しました。
会社勤めのころにはまったくわからなかった現実の世界にうちのめされつつ、
ひたすら成功だけを思い描いた日々。
つらい日々を乗り越え(今思えば「全然つらくないぞ」と中村青年にいいたいが・・・)、
手元にはたくさんのリストが入手でき、体験イベントに向けての案内を電話や手紙で伝え続けました。
そして、ついに体験イベントの当日をむかえることができました!
ここまでしっかりと広告活動を行っている保育所は当時はなかったので、かなりの反響があり、
23名の定員の保育所になんと63名もの見学者が来てくれたのです!!
もうセオリー通りの展開です!
イベント最中はこころの中で、「苦労は報われる!やればできるぜ!!」
って歓喜の雄たけびを上げておりました。
だって、定員の3倍の方がいらっしゃたんだから、
そりゃすぐに子どもたちでいっぱいの保育所になるだろうと誰だって思いますよね?
が、しかし、現実はそんなに甘くなかったのです。
次回は「利用者1名からの再起」をお送りいたします。
——————————————————————
株式会社SHUHARI
保育園元気キッズ 代表 中村敏也
発行:株式会社SHUHARI
※ 当メールマガジンの内容の無断複製・転載・使用を固く禁じます。
Copyright 2007 SHUHARI Corporation. All Rights Reserved.
中村敏也のメールマガジンでは
・保育・児童発達支援の経営のためになる情報
・オンラインセミナーのご案内(メルマガ読者限定案内あり)
・講演会のご案内
などをお送りしています。
困っている保育所の足元を見た高額な人材紹介会社に頼らず、自力で採用できる力を、すべての保育所が持つことができれば、より良い保育環境が広がるはずです。
子どもたち、保護者、保育士にとって、とても幸せな世界になることを願って、少しでもお力になれれば幸いです。
※メールが届かない場合、携帯メールの受信設定、迷惑メールの設定などをご確認ください。
@shuhari.bizからのメールを受信できるようにしておいてください。
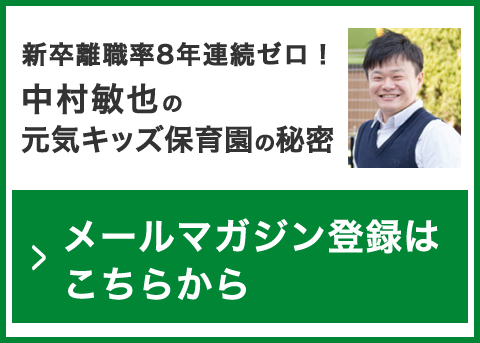
2020年9月16日
参考:メルマガバックナンバー 2020.07.30 配信
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密 vol.6 地域社会を変える保育園への道1
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密
地域社会を変える保育園への道・その1「中村青年、海を渡る」
こんにちは。
株式会社SHUHARI 中村 敏也です。
現在、元気キッズでは、保育、福祉の壁を超えてさまざまな取り組みを実施しています。
具体的には、保育所、児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問保育、相談支援など。
これから数回に分けて、保育所から始めて、どのように新しいサービスを地域で展開していったのかをお伝えいたします。
■保育所開所は、保育士でもなく、親族からの引き継ぎでもなく
保育所を運営しているとよく聞かれるのが、
「親から引き継いだのですか?」「保育士だったのですか?」
「なぜ保育所をつくったのですか?」という質問。
代表としては年齢が比較的若く、顔も童顔のため、「きっと親族から受け継いだのだろう」と憶測でお話しされる方が多く、
「自分の代で開所しました」
「保育士ではなく、まったく別の業種で働いていました」
と答えると、非常に驚かれることが多いです。
ギャップに驚かれるのが、正直少しだけ気持ちが良いです(笑)
そこで、まずは保育所を作ったきっかけからお話しします。
■学生時代の中村青年
もともと学生時代から「会社に務めるよりも、ネクタイをしないで自由に働きたい。
ネクタイしない職業といえばアーティストだ!」と思い込んでいるような、
非常に単純で世間知らずのかわいらしい青年でした。
自分に何ができるのか自問自答を繰り返す中、日本だけでなく世界を見てみようと
まずはアメリカのロサンゼルスと、ニューヨークへ旅行をしました。
人と違うことに憧れていたモラトリアム真っ最中の中村青年は、
アーティストになりたいならまずは本物をみなければと、
ニューヨーク滞在中に美術館に行けるだけ行きました。
またロサンゼルスでは、サンタモニカからベニスビーチまでの間をよく散歩し、
たくさんの路上アーティストや、個性豊かな方たちに触れました。
そこで、感じたのが、なんと「アートって自己満足だな」と。
「アーティストになりたい」というのはただの自己欺瞞かなと気がついたのです。(気づいてよかった。)
帰国後、自分は何が本当にやりたいのかをさらに自問自答した時、
司馬遼太郎の『竜馬がゆく』を読み、「これだー!」という強い思いが湧き出てきました。
竜馬のように、「社会的に意義のあることをやりたい!!」と強く思ったのです。
まさに単純の極み!
そこで改めて、自分に何ができるのか見つけるためにアメリカへの留学を決意し、
大学3年の終了時に1年間の留学へ旅立ちました。
アメリカ留学中はほとんどすべてのことを自分で考え、決断しなければならない日々に、初めは戸惑いましたが、
最終的には「生き抜くたくましさ」みたいなものが身につき、
『とにかくやってみればどうにかなる』という信念が根付いたように思います。
日本にないものがたくさんあり、また日本の方が数倍進んでいるのではないかと思うこともあり、毎日が学びの日々でした。
その頃から「自分で事業をやりたい」と思うようになりました。
■激務の会社員時代
帰国後、今の自分にはまず社会人経験が必要だと思い、
若いうちから色々と任せてくれる会社が良いと、勢いのある上場会社へ就職しました。
早朝から深夜まで働き本当にたくさんのことを学ばせていただきました。
仕事を定時に終えることができず、とにかく時間がもったいなくて、
通勤時間ももったいないのでで会社の寮に入らせてもらい、朝7時から深夜2時まで働く日々。
猛烈社員の典型的な姿。
みんながワーカホリック状態なので、居心地はとても良く、戦友がたくさんできました。
しかし、過酷な労働環境の中、離脱する人もたくさんいて、若者が消費されているなという感じも否めなかったです。
*福祉の世界の「やりがいの搾取問題」と似ていると今なら思えます。
当時、私は幸運なことに上司にも恵まれ、とても責任ある仕事を任せてもらえたので本当に楽しく仕事に取り組めていました。
いわゆる「ゾーン」に入っていた思います。
2年間、がむしゃらに仕事に取り組んだ後、
「そろそろ自分のことに向き合おう」と、仕事以外のことに目を向けはじめた、そんなときに、
とても驚くことがあったのです。
■保育所の開所を決意
従姉妹が結婚をし、めでたく子どもが生まれた後に、
「預ける場所がなくて困っているんだ」とぼそっと話すのを聞いたのです。
「保育園に入れないなんてことある?」なんて思ったのですが、
この時は平成14年でしたが、実際調べてみると、待機児童問題がこの時からものすごくあったのです。
そこで、保育のことを調べていくと、どんどん興味が出てきて、保育の学校にも通いました。
学校には社会人の方も多く、保育や福祉に関する知識が豊富な方ばかり。
ご自身で保育所を運営したいという方も数名いたので、たくさん刺激を受けました。
その反面、経営という視点で保育を捉えている人がほとんどいなく、
自分の強みであるマーケティング力が生かせるのではないかという思いが湧いてきました。
そして、これこそ社会的に意義のある事業だと思い、「待機児童解消!」のために保育所の開所を決意したのです……
次回は、開所後の奮闘記、をお届けします!
——————————————————————
株式会社SHUHARI
保育園元気キッズ 代表 中村敏也
発行:株式会社SHUHARI
※ 当メールマガジンの内容の無断複製・転載・使用を固く禁じます。
Copyright 2007 SHUHARI Corporation. All Rights Reserved.
中村敏也のメールマガジンでは
・保育・児童発達支援の経営のためになる情報
・オンラインセミナーのご案内(メルマガ読者限定案内あり)
・講演会のご案内
などをお送りしています。
困っている保育所の足元を見た高額な人材紹介会社に頼らず、自力で採用できる力を、すべての保育所が持つことができれば、より良い保育環境が広がるはずです。
子どもたち、保護者、保育士にとって、とても幸せな世界になることを願って、少しでもお力になれれば幸いです。
※メールが届かない場合、携帯メールの受信設定、迷惑メールの設定などをご確認ください。
@shuhari.bizからのメールを受信できるようにしておいてください。
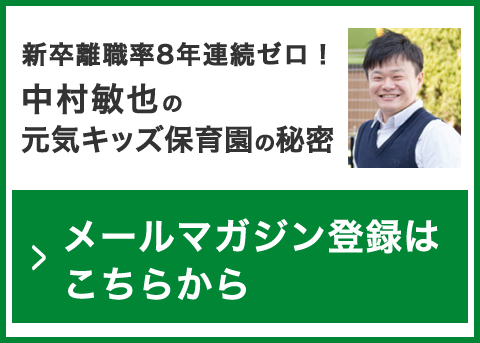
2020年9月12日
参考:メルマガバックナンバー 2020.07.16配信
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密 vol.5「理念+文化+ルール」で起きた奇跡
中村敏也の元気キッズ保育園の秘密
「理念+文化+ルール」が揃ったことで起きた奇跡
こんにちは。
株式会社SHUHARI 中村 敏也です。
前回、理念は文化に支えられ、文化はルールが作るというお話をしました。
では、この3つが定まって起きた「元気キッズの奇跡」をちょっとシェアします。
『8年連続・新卒離職者ゼロの奇跡』
誰も意見を言えないような硬直した組織の時代を経てきた元気キッズですが、
「子どもたちの笑顔のためには、まずは働く職員が笑顔にならなければ」という思いで、ガムシャラに理念やルールを作っていきました。
改革から5年たっところ、ふと気づくと、離職者がほとんどいなくなっていたのです。
もちろん文化に馴染めない方たちはこの過程で残念ながら去っていきました。
そして気付いたら、私が変わろうと決意し、行動を起こしてから入社した新卒の職員が誰一人やめないでいてくれていたのです!!
個人面談の時に新卒入社の職員に、
「なんで元気キッズを選んでくれたの?」と聞くと
「園長先生の話を聞いて、職場体験に行ってみたいと思い、実際 体験に入ったら、
園長先生の言った通り、みなさんが楽しそうに仕事をし、とてもやさしかったからです」
という声が多くありました。
思い返せば当時、ミーティングでも面接時でも、
元気キッズの思い、方針、職員の4つの約束などを、
熱を込めて説明し続けていました。
面接ではあまりにも熱く語りすぎたため、
細かい内容よりも、私の熱意、いや気迫みたいなものに圧倒されて、
体験に来てくれなかった方もいたかもしれません。
とにかく熱量だけはそれくらいハンパなかった(笑)
むしろ熱量しかなかった。
だって、まだ実績がなかったので、ビジョンを伝えることしかできなかったので。
そして、気づくと、
8年連続で、新卒の離職が0人の保育園を達成していました。
『取材が来るようになってからの奇跡』
奇跡のような離職者ゼロ。
特に保育業界では、大量離職で園の運営が困難になるケースが全国的なニュースになるような時代、
元気キッズの離職ゼロはとても目立ったようで、
いくつかのメディア、新聞などから取材が来るようになりました。
少しでも元気キッズの知名度をあげ、職員がプライドを持って働ける園にしたい
という思いから積極的に取材に応じました。
するとどうでしょう。
ここでも大きな流れが起きたのです。
記事を見た保育士から、応募の連絡が入ったり、
県庁から、仕組みを教えてほしいと担当者が来たり……
この頃から自治体から、新しいオファーや公募に参加してほしい
と打診をいただくことが多くなり、近年の新規開園ラッシュに繋がりました。
『セルフマネジメントの組織になってからの奇跡』
「理念+文化+ルール」が定着していくと、職員の関係性がとてもよくなり、
何より「やさしい人」が増えました。
私自身も「やさしい人」に来てもらいたいと思って、採用活動に取り組んでいたため、
スキルだけでない、人として信頼できる人が多く集まって来ました。
思いに共感した職員は、ただ「やさしい」だけでなく、
しっかりと自分の考えを持って仕事に取り組む方が本当に多いのです。
また「今よりも少しでも良いことはすぐやってみよう!」の精神が、
職場全体に広がった結果、
自分たちが必要と思うことを どんどんやってくれるようになりました。
そして、新しい事例を会議で共有、そこで他の施設にも導入という流れができました。
結果、セルフマネジメントの組織に変わっっていったのです。
自らが考えて、やりたいことを実現していく組織へ変貌をしていきました。
『私自身にも起きた奇跡』
変革当初は、実は私自身はあまり得意でない「強烈なリーダーシップ」を無理やり発揮して組織を変えていきました。。
しかし、組織が変わった今、そのようなスタイルは必要なくなりました。
本来の自分に戻れたことでほっとし、心の中に少しの自信と余裕が生まれたのです。
これは、私にとって大きな奇跡でした。
悩める園長先生にとって、この「少しの自信と余裕」って、心から手に入れたいものなのかなと思います。
・「安心して任せられるチーム」があること
・心に余裕ができること
この2つが揃ったことで、これまで手をつけられなかった新しい課題にも取り組むことができるようなったのです。
次回は、社会を変える保育園への道をお届けします!
——————————————————————
株式会社SHUHARI
保育園元気キッズ 代表 中村敏也
発行:株式会社SHUHARI
※ 当メールマガジンの内容の無断複製・転載・使用を固く禁じます。
Copyright 2007 SHUHARI Corporation. All Rights Reserved.
中村敏也のメールマガジンでは
・保育・児童発達支援の経営のためになる情報
・オンラインセミナーのご案内(メルマガ読者限定案内あり)
・講演会のご案内
などをお送りしています。
困っている保育所の足元を見た高額な人材紹介会社に頼らず、自力で採用できる力を、すべての保育所が持つことができれば、より良い保育環境が広がるはずです。
子どもたち、保護者、保育士にとって、とても幸せな世界になることを願って、少しでもお力になれれば幸いです。
※メールが届かない場合、携帯メールの受信設定、迷惑メールの設定などをご確認ください。
@shuhari.bizからのメールを受信できるようにしておいてください。
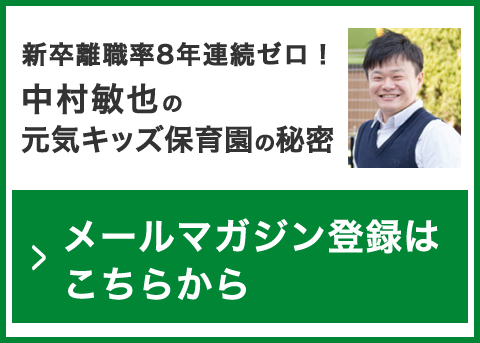
2020年9月3日